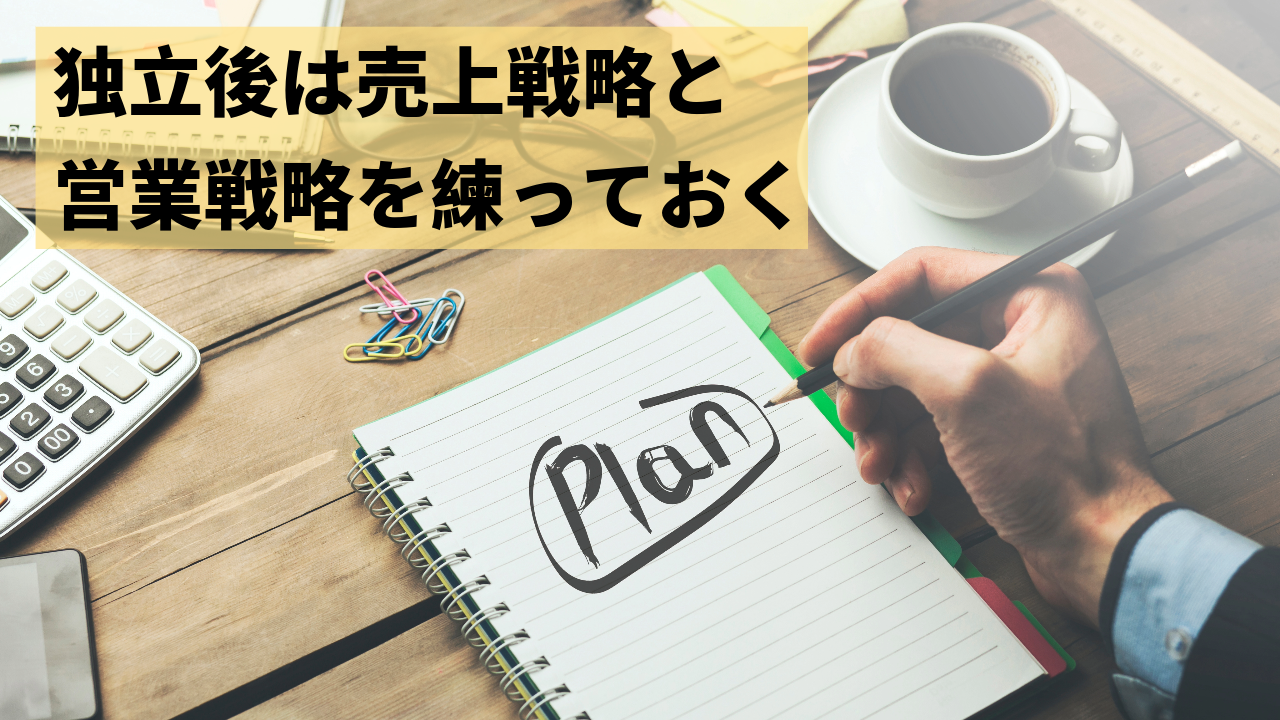独立する前からの不安として営業活動をどうしていけばいいか、というのがあります。いろんな方法があるので気になったことはやってみるのがよいですが、営業活動はじめる前に売上の戦略も練っておいた方が良いです。
取るべき方法が自然と決まることもありますので、どういう顧問先でいくらの売上を考えるか、そこから練ってみましょう。
独立後の売上計画
おなじ1,000万円の売り上げだとしても以下の内容だと全然違う、というのは税理士をしていればなんとなくわかるはずです。
- 年間100万円の顧問先10件
- 年間65万円の顧問先15件
- 年間40万円の顧問先25件
- 年間30万円の顧問先33件
- 年間20万円の顧問先50件
- 年間10万円の顧問先100件
全部が全部同じ顧問料というわけではないでしょうけれど平均したとしてこの年間の顧問料と考えてもらってもよいです。
私の場合は相続税申告業務に取り組みたいと独立前からも考えていましたので、相続税申告も含めた売上の計画を当初から考えていました。
そうなるとまた違って見えてくるかと思います。
記帳代行をするのかしないのか、報酬の金額もそうですが自分の時間を取れるかどうか、というところにも関わってきます。
いろんな要素が絡み合ってくるのでやはりシミュレーションしておくに越したことはないです。
途中で流れが変わることもありますし、シミュレーション通りにいかないということもしばしばあるでしょう。
私の場合でいうと漫画家や同人作家、同人クリエーターのお客様が多いのですが独立前はもちろん独立後もしばらくは全く想定していませんでした。
独立後に事務所ホームページからご依頼をいただいたおひとりのかたからの関わりから学ぶことや経験することが多くあり、そこから営業活動もそちらの分やにシフトしたという面があります。
こうして何がキッカケになるかわかりませんが仕事の中身だったり特定の業種に強くなったりというのはあるので、地道に好奇心を持って取り組むというのも大事かなと。
経費はひとりでやっている実感としては抑えられるところは抑えて、会計税務ソフトはそれなりにしっかりしたものを使って年300~400万円というところです。
営業のしやすさ
年間報酬が高くなればなるほど営業は難しくなります。成約率が下がるということです。
では最初は年間報酬を低く抑えて成約率を上げればよいかというとそれはそれでこちらが割を食う可能性が高くなります。
この辺りの難しさというのは営業活動について回ります。
営業が得意だ、苦にならないということで自信があればどんどんやっていけばいいでしょうけれど、税理士についてはそういうタイプは少ない印象です。
安請け合いするとあとで自分の首を絞めてしまうことになりかねません。
いくらの価格設定にするのか低すぎると受けやすくはなるけどハードになるでしょうし、高すぎると受けにくくはなるので仕事がない期間が生まれやすいです。
仕事がない状態というのは思っているよりもつらいもので、自分で作っていく意識も大切です。
独立すると税務だけではなくやるべきことはあり、特に営業活動については細く長く続けていくほうが効果が出やすいと考えています。
相続業務については特にいつ受託できるかが全くわからないことが大半で、相続対策からといっても実際の申告に至るまで時間スパンが長いです。
そうはいってもご依頼をいただくときには重なったりもしますのでもし相続業務をやりたいなら顧問で自分の仕事に充てる時間を目いっぱい使わないことです。
顧問業務のほうが営業の難易度は低いというのが私の実感としてあり、どんどん受けてしまいがちですしそうしたくなるものです。
安定はいらない、と思いながら独立をしても食べていけるようになるまで時間を要することもあるでしょうし、手元のお金がどんどん減っていくことで不安も強くなります。
報酬が安い方が当たり前ですが価格勝負で勝てますから仕事は取りやすいのですが、中長期的な目線で見ると自分を苦しめることになりかねませんのでバランスをどうとるかは考えておいた方がいいです。
営業活動での成約率と報酬には相関関係があるのでそのあたりも十分に意識しつつ営業活動をしていくのがおすすめです。
まとめ
当初の予定とは変わってきた部分ももちろんありますが、営業活動での成約率、ご依頼の多い少ないと報酬には相関関係があると私は考えています。
それもありますしたくさん一気に受託すると多分業務が回らなくなって、人を雇ってもうまくいかないみたいなケースは見かけます。
計画を練ってみて変えるべきところは変えつつ自分に合った内容に修正していくのがよいと思ってやってます。